はじめに
骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)は、骨盤の底にある筋肉の集まりで、内臓を下から支える「身体の土台」のような存在です。
この筋肉群が弱ると、尿漏れ・臓器の下垂・姿勢の崩れなど、さまざまなトラブルが起こります。
特に出産後や加齢により、筋力が低下しやすいため、男女問わず日常的なケアが大切です。
骨盤底筋群の構造と役割
骨盤底筋群は、骨盤の下部に膜のように広がり、仙骨・尾骨・恥骨・坐骨をつないで内臓を支える構造を形成しています。
主な筋肉は以下の通りです:
- 恥骨直腸筋(ちこつちょくちょうきん):直腸を引き上げ、排泄コントロールを助ける
- 恥骨尾骨筋(ちこつびこつきん):尿道・膣・肛門を取り囲み、締める働きを持つ
- 腸骨尾骨筋(ちょうこつびこつきん):骨盤底を後方で支える
- 会陰筋群(かいいんきんぐん):骨盤底の下層で、外尿道括約筋や肛門括約筋と連動
これらの筋肉が連携し、以下のような重要な働きを担っています。
- 内臓を支えて下垂を防ぐ
- 排尿・排便をコントロールする
- 姿勢の安定(体幹の一部として機能)
- 呼吸運動・腹圧調整の補助
骨盤底筋群が弱くなる原因
骨盤底筋群の機能低下は、以下のような生活習慣・身体状況が原因で起こります。
- 出産や加齢による筋力低下
- 長時間の座位や運動不足
- 姿勢の崩れ(骨盤後傾や猫背)(関連記事:「さまざまな姿勢による身体への負担」)
- 肥満や便秘による腹圧の上昇
- 咳やくしゃみの繰り返しによる負担
これらの要因で骨盤底筋群が緩むと、尿漏れ・頻尿・骨盤の不安定化などが生じやすくなります。
骨盤底筋群の不調による日常生活への影響
骨盤底筋群が弱ると、内臓を支える力が低下し、姿勢や歩行にも影響します。
特に、骨盤の安定が崩れると腰椎の動きが乱れ、腰痛(関連記事:「腰痛の原因と改善方法」)が起こりやすくなります。
また、骨盤の傾きによって坐骨神経痛(関連記事:「坐骨神経痛とは?原因と対策」)を誘発することもあります。
さらに、骨盤が後傾するとハムストリング(関連記事:「ハムストリングの解剖学」)が硬くなり、
大腿四頭筋(関連記事:「大腿四頭筋の解剖学」)とのバランスが崩れて下肢全体に影響を及ぼします。
その結果、姿勢が崩れやすく、腰・股関節・膝への負担が増すこともあります。
セルフケア・骨盤底筋群の鍛え方とストレッチ
骨盤底筋群は、意識して動かすことで強化できます。
1. 骨盤底筋トレーニング(ケーゲル体操)
- 仰向けで膝を立て、骨盤の下を意識します。
- 尿を我慢するように肛門と膣(または会陰部)を軽く締める感覚で5秒キープ。
- その後ゆっくり緩め、10回を1セットにして1日3セット行いましょう。
2. 呼吸と連動したエクササイズ(関連記事:「呼吸と身体のつながり」)
- 息を吸うときに骨盤底を軽く緩め、吐くときに締めるようにします。
- 呼吸と合わせることで、横隔膜(関連記事:「横隔膜の解剖学」)・腹横筋(関連記事:「腹横筋の解剖学」)・多裂筋(関連記事:「多裂筋の解剖学」)との連動が高まり、体幹安定にも効果的。
3. 脊柱起立筋ストレッチ(関連記事:「脊柱起立筋の解剖学」)
- 骨盤を安定させるためには背面の柔軟性も大切です。
- 両手を前に伸ばし、背中を丸めながらゆっくり前屈し、脊柱起立筋を伸ばしましょう。
骨盤底筋群と背面の筋肉のバランスを整えることで、正しい姿勢と骨盤の位置を保ちやすくなります。
👉その他のストレッチはInstagramをご覧ください
まとめ
骨盤底筋群は、身体の「底」を支えるインナーマッスルであり、姿勢・内臓・排泄・呼吸のすべてに関係する重要な筋肉群です。
弱化すると、尿漏れや腰痛、姿勢不良などの原因になるため、日常的なトレーニングとストレッチでケアすることが大切です。
正しく使えるようになると、体幹が安定し、姿勢も自然と整っていきます。
関連記事👇
アクセス案内
整体サロン縁jointは、京都市中京区堺町通りにあります。
阪急「烏丸駅」地下鉄「四条駅」から徒歩約3分、錦市場からはすぐ。
店名:整体サロン 縁joint
住所:〒604-8123 京都府京都市中京区八百屋町538-1日宝堺町錦ビル3階1号室
営業時間:11時~21時 (19時以降は完全予約制のため最終受付18時30分)
定休日:木曜日

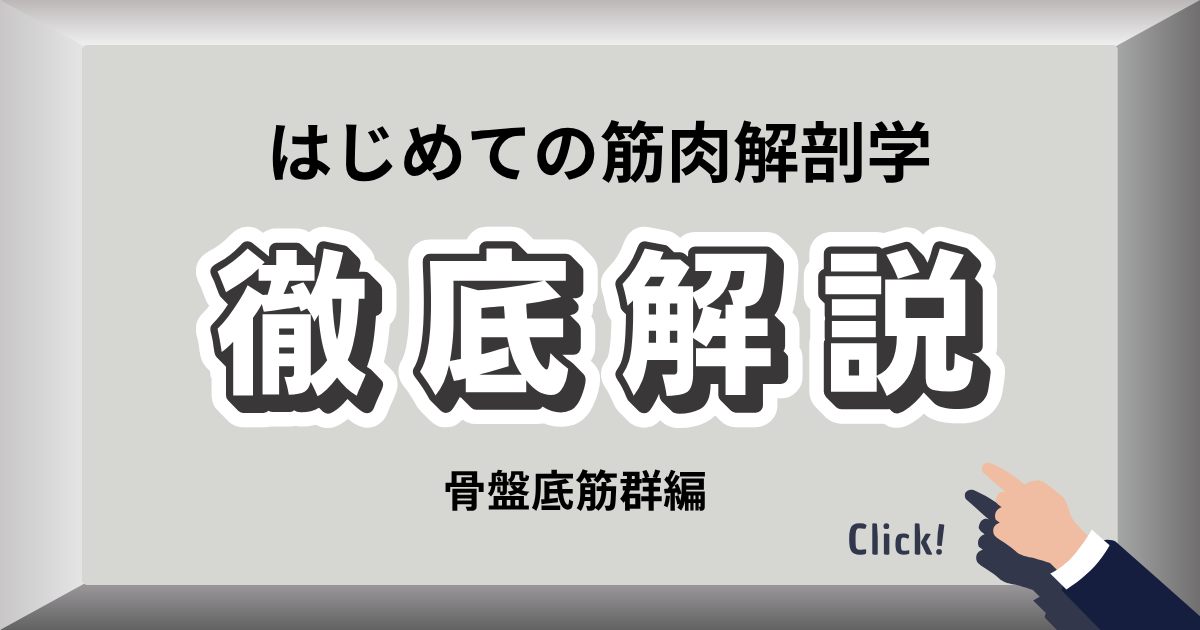
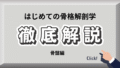
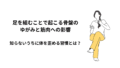
コメント