
はじめに
胸椎(きょうつい)は、背骨の中央に位置する12個の椎骨から成り立ち、肋骨とつながって胸郭を形成しています。心臓や肺といった重要な臓器を守るだけでなく、呼吸や姿勢の維持に欠かせない役割を持っています。さらに、胸椎から出る神経は多くの内臓に関係しており、そのつながりを示したものが「メリックチャート」です。本記事では、胸椎の基本情報と内臓との関係、不調時の影響やケア方法について解説します。
胸椎の基本情報
胸椎は頸椎(首)と腰椎(腰)の間にあり、動きは比較的少ない構造ですが、全身の健康に大きな影響を与えます。
- 位置:首の下から腰の上まで、背中の中央部分
- 数:12個(T1〜T12)
- 特徴:肋骨と関節をつくり、胸郭を安定させる
- 役割:体幹の安定、呼吸のサポート、背骨全体のバランス維持
胸椎が硬くなると姿勢不良や呼吸の浅さが起こり、全身の不調につながります。
関連記事👇
胸椎と内臓のつながり(メリックチャート)
胸椎から分岐する神経は、さまざまな内臓と関わっています。歪みや硬さがあると、その部位に関連する臓器の働きが乱れることがあります。
- T1:腕、手、食道、気管支
- T2:心臓、冠動脈
- T3:肺、気管支、胸膜
- T4:胆のう
- T5:肝臓、血液循環
- T6:胃
- T7:膵臓、十二指腸
- T8:脾臓
- T9:副腎
- T10:腎臓
- T11:尿管
- T12:小腸、大腸(結腸の一部)
胸椎の不調による影響
胸椎の部位ごとに、身体に表れる影響は異なります。
- 上部胸椎(T1~T4):呼吸器や心臓系の不調(息苦しさ、動悸、肩こり)
- 中部胸椎(T5~T8):消化器系の不調(胃もたれ、肝機能低下、消化不良)
- 下部胸椎(T9~T12):泌尿器・内分泌系の不調(疲労感、腎臓・副腎への負担、便通異常)
日常生活への影響
胸椎が硬くなると猫背や巻き肩といった姿勢の悪化が起こりやすくなります。その結果、呼吸が浅くなり酸素の取り込み量が減少し、集中力や体力の低下につながります。また、胸椎とつながる内臓の働きも乱れるため、慢性的な疲労や消化不良などが起こることもあります。デスクワークや長時間の座位が多い方は特に注意が必要です。
有効なストレッチ方法
胸椎を柔らかくするには、胸を開く動きや回旋(ひねり)を取り入れるのが効果的です。
- 胸椎伸展ストレッチ
ストレッチポールを背中に縦に置き、仰向けに寝て両手を横に広げ、深呼吸を繰り返す。
→ 胸椎の伸展が促され、呼吸が深まります。 - 胸椎回旋ストレッチ
横向きに寝て膝を曲げ、上側の腕を大きく開いて胸をひねる。
→ 胸椎の回旋が改善され、肩や背中の緊張が和らぎます。
→その他のストレッチはInstagramをご覧ください。
まとめ
胸椎は姿勢や呼吸を支えるだけでなく、神経を通じて多くの内臓と関わる重要な部位です。硬さや歪みを放置すると、肩こりや腰痛だけでなく、呼吸器・消化器・泌尿器などの不調にもつながります。日常的に胸椎のストレッチを行い、柔軟性を保つことが全身の健康維持につながります。
アクセス案内
整体サロン縁jointは、京都市中京区堺町通りにあります。
阪急「烏丸駅」地下鉄「四条駅」から徒歩約3分、錦市場からはすぐ。
店名:整体サロン 縁joint
住所:〒604-8123 京都府京都市中京区八百屋町538-1日宝堺町錦ビル3階1号室
営業時間:11時~21時 (19時以降は完全予約制のため最終受付18時30分)
定休日:木曜日

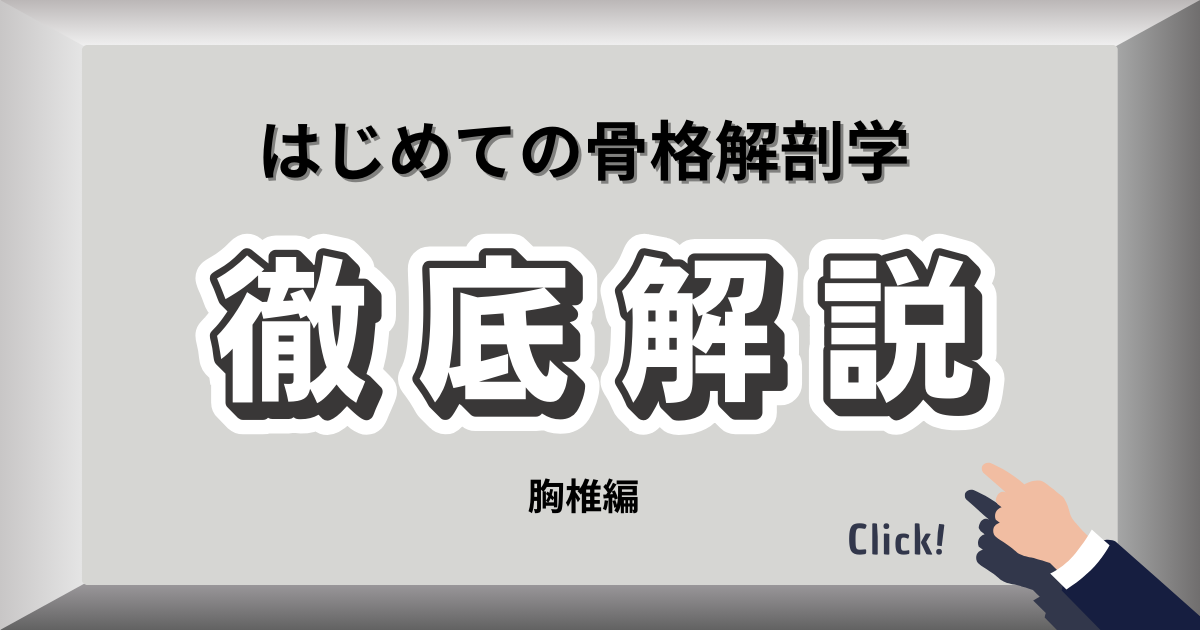
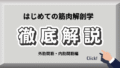
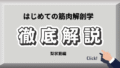
コメント